- 1人~4人
- 15分~30分
- 10歳~
- 2024年~
カスカディア・ローリング:波立つ川18toyaさんのレビュー
【レビュー】本家とは違うプレイ感ながら、シート4種の構成が秀逸な良作紙ペン!
【評価 8/10】
ダイスロール&カードフリップ融合型紙ペン
/post_image_85125a2f-ea64-4169-a977-67bac610731b.jpeg)
本作は2022年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞した名作パズルゲーム「カスカディア」のシリーズ作品。
本家カスカディアは生息地タイルと動物トークンの並べ方をなるべく高得点にしたいと思いつつ、全部をうまく組み立てることは至難のため、どこまで理想を追いどこで現実との見切りをつけるかが面白い二層パズルゲームだった。
本作は動物の取り扱いが本家とは大きく異なっており、「これをカスカディアのシリーズと言って良いのか?」と感じる方もいるかもしれない。
しかし、4シート全てを遊んでみた筆者の感想は、本作は「カスカディア」の名を冠するに遜色無い紙ペンゲームだと感じた。
さぁ、再びカスケード山脈のふもと、カスカディア・バイオリージョンを旅する時間がやって来た。
以下では、本作の概要や醍醐味について説明していきたいと思う。
基本の流れ
シートがA〜Dの4種あり、どのように書き込みを入れてどう得点化するかはシートごとに異なるが、共通の流れは以下の通りとなる。
1 中央ダイスと個人ダイスのロール
2 動物の獲得+ダイスアクション(任意)
3 生息地カードの達成(任意)
4 ラウンドの終了
上記の4フェーズを20ラウンド繰り返してゲームは終了。得点計算を行い、最高得点を取ったプレイヤーの勝利となる。では以下でそれぞれのフェーズについて見ていく。
各フェーズの概要
まず 1 のダイスロールでは4つの中央ダイス(少し大きな青ダイス)と個人ダイス(小さめの茶色いダイス)2個を振る。中央ダイスは誰が振っても良い。個人ダイス2個は各自で振る。/post_image_5dd95099-dcec-4b53-b166-07e35d006419.jpeg)
ここで個人ダイスの配り方に注意!熊の面があるダイスと鷹/鮭の面があるダイスを組み合わせて各自が持つことを覚えておこう。上記2種の個人ダイスは面の構成が違う。
次に 2 の動物の獲得。中央ダイスと個人ダイスを組み合わせて動物を1種選び、各自が獲得する。これは他のゲームでの資源獲得と同様に考えて良いだろう。
例:この出目で熊を取ることにした。中央ダイスで熊1、個人ダイスで熊1、中央ダイスのワイルド(どの動物でも良い)も熊とみなして、合計熊3匹を手に入れる事ができる
中央ダイスは全員共有で、誰かがある動物を取っても中央ダイスは枯渇しないので安心して同じ動物を取っていい。また、1つは「特殊中央ダイス」となっており、効果が他のダイスと異なる。詳細はルールブックでご確認を。
ダイスから動物を獲得する際に、任意で自然トークンを消費してダイスアクションを実行することもできる。ダイスアクションは1種類の動物を異なる種類の動物とみなすことができたり、2種類の動物を獲得できたりする。あくまで「みなす」のであって、中央ダイスの面を変える訳ではないので注意。
獲得した動物は集計シートに書き込む。
この集計シートを見て「何これ?」と不安になる人もいるかもしれないが、単に駒やトークンでやる事を紙に書いているためゴチャゴチャして見えるだけだ。何なら木駒に置き換えて遊んだ方が分かりやすいかもしれない。
次いで 3 のフェーズで生息地カードを1枚だけ達成できる。しなくても良いし、そもそも動物が足りなくて達成できない場合もある。その場合はこのフェーズを単に飛ばす。
生息地カードは達成カードがセットになる。コンポーネントには12枚の達成カードがあり、それぞれ独自の効果を持つが、大きく分けると2種類。生息地を達成する時に必要な資源を割り引いてくれるもの(割引達成カード)と、達成した後おまけをもらえるもの(ボーナス達成カード)だ。/post_image_fe0124ef-8ee1-430e-a3d9-43abafa1cf44.jpeg)
なお、1ゲームで使うのは4枚。シナリオチャレンジで遊ぶ場合はシナリオごとに使用する達成カードが指定されているが、フリーで遊ぶならランダムに配置する。
各生息地が要求する動物を支払うことができれば、まずはその生息地カードの下にあるボーナス達成カードの効果を受けることができる。この処理順は特定の達成カードで重要になるので、忘れず先にボーナス効果を受け取ろう。
例えば、この川を達成したら、セットの達成ボーナスカードから自然トークンを1つ得る事ができる
その後、選択した生息地カードの種類及び探検値に従って、環境シートを書き込む。詳細はルールブックを参照して欲しい。生息地から得られるボーナスもこの時獲得する。
最後に、環境シートから獲得条件を満たした資源や勝利点を得る。これはシートごとに異なる。
最後に 4 ラウンドの終了処理に入る。生息地カードは一つ右にずれ、その生息地カードがあった場所に山札から捲った新たな生息地カードを置く。
/post_image_f58088da-cb21-455e-a33c-e31be8ad6f81.jpeg)
/post_image_4caf3c12-2cf7-4a3a-9e6e-c03b6aab9444.jpeg)
各生息地カードはラウンドが進むごとに右にスライドしていくが、達成カードは移動しないので、生息地と達成カードの組み合わせが毎ラウンド少しずつズレていく。どの達成カードとセットの時にどの生息地を達成するかが本作の悩ましいポイントだ。割引を受けて達成を容易にするか?ボーナスをもらうか?
やがて、4枚の達成カードとセットにならない場所まで生息地が押し出されたら、その生息地は捨て札となり、もはや達成することができなくなる。
/post_image_e2d53b47-0410-4800-85f7-4461b0974dc9.jpeg)
/post_image_82586e43-a331-4890-bb55-fbabdcf2948f.jpeg)
大事な生息地は押し出される前に達成しておこう。
19ラウンド目の第 4 フェーズで生息地カードを場に置くと、生息地山札は尽きる。これがゲーム終了が近い合図だ。
/post_image_0784bdec-3739-4936-ab10-3d16459fb31c.jpeg)
/post_image_024a48ab-c68e-4baa-820e-78c9b63b9372.jpeg)
20ラウンド目の 1 〜 3 フェイズを終えたら得点計算を行い、最も勝利点が高いプレイヤーがゲームに勝利する。
シートと得点計算
得点計算の方法は環境シートごとに異なる。シートA〜Cでは主に生息地から点数を得るという点では共通しているが、単純に生息地カードの探検値が大事なシートもあれば、「どこのマスを囲うか」の配置パズルが大事になるシートもある。
さらにシートDでは本家カスカディアのように動物の得点がメインになる。各動物は種類ごとに得点となる配置が異なっているが、配置と得点の関係は本家カスカディアのタイプAにかなり似ているので、本家を遊んだことがある人であればすぐに理解できるだろう。
本家カスカディアとのプレイ感の違い
さて、ここまでローリングの大まかな流れをザックリ見たきたが、はっきり言おう。
本家とローリングのプレイ感は相当違う。
/post_image_9484e241-c7a4-4285-81c0-24014edc4606.jpeg)
本家カスカディアでは4つの「生息地タイル+動物トークン」ペアの中から1つを選び、自分が既に配置したタイルに隣接するように生息地タイルを置きつつ、動物トークンを生息地に載せていくゲームだった。
生息地はなるべくボーナスを得られる7枚までは同種を連続させて置きたい。が、各生息地タイルにはそのタイル上に置ける動物も描かれており、生息地を繋げつつ動物でも高得点を取れる配置にすることがなかなか難しい。ここが本家カスカディアの悩みどころであり醍醐味だ。/post_image_71e3b4f4-5cf5-4d38-b4fb-3fc88ef80989.jpeg)
一方で本作・カスカディアローリングでは、ダイスを振って動物を集め、その動物を支払って生息地を達成し環境シートに記入していくのがゲームの根幹だ。
/post_image_8deb4582-79b0-4b45-89c9-cb2716ebc4c1.jpeg)
本家カスカディアでは二層パズルの主役だった動物をローリングではリソースのように扱っており、逆に本家では若干脇役ぎみだった生息地がローリングでは紛れもない主役となっている。これは面白い対比だ。
また、本家では誰かが取った組み合わせは他の人が使えなくなる、という排他的なインタラクションがあったが、ローリングでは他の人に干渉する方法はなく、極端に言えば全員が同じ種類の動物を獲得する場合すらある。こうしたインタラクションの差も、ローリングと本家の違いを感じさせるかもしれない。
また、これは長所だがローリングは紙ペン独特の「シート各所に散りばめられたボーナス」を備えている。コンボも発生して当初思っていたより多くのものが獲得でき、紙ペンらしい爽快さを楽しめる。
このように、本家カスカディアとローリングの相違点は色々ある。ただし、他の作品でも同じシリーズでありながらゲーム性が異なることも珍しくない(例えば西フランクシリーズ、世界の七不思議本家・デュエル・建築家たち等)。
問題はそのゲームが面白いかどうかだ。そして、まさしく本作カスカディアローリングはしっかりした面白さを備えていると筆者は評価している。
本作の醍醐味
本作の面白さの源泉は4種シートの重層的な構造だ。
/post_image_4dfef426-3906-402e-ae9d-bbe2547d15da.jpeg)
本家カスカディアでは動物で高得点を取れるように注意しながら、生息地タイルもできるだけ同種で繋げていきたいがなかなかうまくいかない、という悩ましさが面白ポイントだった。こうした自由な配置の楽しさをそのまま紙ペンで再現することは難しいだろうし、仮に出来たとしても逆に「本家じゃなく紙ペンで遊ぶ理由は?」となってしまうかもしれない。
その点、ローリングでは生息地の場所はシートごとに固定しつつ、生息地カードを達成した時に生息地の中に探検値や動物を書き込んだり、またはペンで生息地を囲うことができ、初めて生息地が有効になる(つまり得点できる状態になる)。自由に配置するのではなく、既に印刷された地図の中で5種の生息地(山、森林、大草原、湿地、川)のどこを有効にしていくかという戦略がゲームの主題となる。これは紙ペン化の方法として冴えたやり方だ。
ただし、こうした「動物をリソースとして使い、生息地カードを達成していく」プレイ感には慣れが必要となる。特に本家に慣れているプレイヤーほど、動物をリソースとして使うという感覚には最初戸惑いを覚えるかもしれない。
よって、シートAがチュートリアルとして機能する。Aは最もシンプルで、システムの根幹である「動物リソースを使って生息地カードを達成する」という流れだけを注視すれば良い。/post_image_7a1ac607-bdba-48d5-b04b-989503eeb859.jpeg)
各プレイヤーもシートAを1、2ゲーム遊べば本作の仕掛けがだんだん見えてくるだろう。そこでお次がシートBだ。各生息地が数直線のように横一列に並んでおり、生息地カードの探検値の使い方がこのシートBから変わる。「達成した生息地カードに書かれた探検値の数ぶん、マスを囲うことができる」と言う、新たなルールが追加される。シートAと探検値の使い方がガラッと変わるが、これも1、2ゲームで慣れることができるだろう。隣接する生息地同士をここまで囲えばこのボーナスがもらえる、と言う仕組みもここで触れることとなる。
/post_image_4bfb140a-7b00-4733-9ed0-d4d8bf547915.jpeg)
ここまで慣れたらシートCは平面に広がる。シートでどこにどの生息地が広がっているかは最初から印刷されて決まっているが、スタート地点の隣接マスから始めてどの生息地を何個囲んでいくか、パズル的な思考が要求される。周囲6マスが全て囲まれたマスは、そのマス自身も囲まれた扱いとする、と言う点も面白い。これを意識すると囲える生息地がぐんと増える。
/post_image_58414670-8642-4d65-9f59-7b28d51dcf1e.jpeg)
ここまでの仕組みに習熟することで、いよいよ最後のシート、Dをプレイする段階に至る。
Dは非常に本家に似たテイストを持つシートで、Cまでは生息地から点数を得るシートだったが、初めて動物の配置により点数を得る仕組みとなる。リソースに落とし込まれたとばかり思っていた動物たちがここで息を吹き返すのは激アツな展開だ。しかも単に動物を配置するような簡単なものではなく、生息地カードと密接な関わりを持っているのだ。/post_image_75c41924-fdb0-45a6-abbd-beb512251661.jpeg)
このシートDに至りカスカディアローリングは、まるで本家カスカディアのように重層的な2層パズルとなる。シートDの難易度は高い。本家と近いことを、ダイスという極めて不確実性の高い仕組みでクリアしなければならないのだから当たり前だ。しかし、このシートを遊び終えた時の満足感は非常に高い。言ってみればシートA〜CはDに至るための必要なステップだったと理解できる。
見た目はアルファベットの羅列だが、Bは熊(bear)、Eはエルク(erk)、Fはキツネ(fox)等を意味しており、脳内ではすっかり本家カスカディアだ。私に絵心があればもう少しエモい絵面に出来るのだが……無念。
筆者はシートAからDを通して遊び、まるで1つのキャンペーンシナリオのようだと感じた。
一気に多くの要素を盛り込みすぎないよう、シートAからDに向かって少しずつ丁寧に要素を積み上げ、最後にはこれらの要素がガッチリと噛み合ってあたかも本家のような2層パズルを織りなす。しかも紙ペンらしいボーナスやコンボも添えて。
最終盤面に至るその構成、その流れは巧緻で美しく、感動すら覚えるほどだ。
なお、終着点のシートDに辿り着いたらあとはDしか遊ぶ気にならないのでは?と問われれば、人によるだろうが私は違う、と答える。「数直線のように伸びた生息地トラックをどのバランスで伸ばしていくか」というシートBもシンプルに楽しいし、「周囲を囲むと中心のマスも自動で囲まれる」シートCもパズルとしての面白みがある。
その上達成カードや生息地カードが変われば当然プレイ感も変わる。これらの要素によってリプレイ性も兼ね備えている。
何より、ダイス目は偉大な乱数生成機だ。仮に同じシートで同じ生息地カード、同じ達成カードの設定だったとしても、ダイス目はいつも異なるのでゲーム展開が毎回異なる。こうした運の翻弄を乗りこなして高得点を出すのはいつだって気持ちがいい。
このように、本作カスカディアローリングはカスカディアの名を冠することに遜色のない、何度も楽しめる良作紙ペンとなっている。これが筆者の結論である。
弱点
このように、カスカディアの名を冠して恥じるところのない名作紙ペン・ローリングではあるが、残念ながら弱点も存在すると言わざるを得ない。
筆者が考える最大の問題点はシートAだ。
/post_image_b3903da0-937a-4603-9cce-6ddf86deb587.jpeg)
上記した通り、シートAからシートDは全てステップを上がっていくために構成されている。Aはその最も初歩であり、「カスカディアローリングとはこういう事をして遊んでいくゲームですよ」とお知らせする役割を背負ったチュートリアルシートだ。
チュートリアルとしてはよく出来ていると思うし、シートDまで遊んだ上で振り返ってみれば「なるほどそういう位置付けか!」と意義が理解できる。ただシートA単体で見るといささか魅力に欠ける、というのが私の感想だ。
むろん構成上、この問題は避けられない。いきなり最初からカスカディア節全開でシートD級を提供されても付いていけないプレイヤーが続出するだろう。
ましてカスカディアはファミリーゲームとして位置付けられているゲームだ。ユーザーフレンドリー性を考えれば当然シートAを入れないという選択肢はない。
ただ、これによりゲームに慣れた人がシートAだけを遊んで「あーカスカディア紙ペンってこんな感じね。大体わかったわ」と「単調で深みのないゲーム」と見切ってしまう危険も招くこととなった。これは悲しむべきことだ。
私としては声を大にして「ローリングはシートAからDまで通して遊んでから判断して!」と言いたい。
あと、これは商業戦略上やむを得ないと理解しつつ言うのだが、シナリオチャレンジ全20シナリオのうち#13〜#20の8シナリオが、本作と対になる作品「カスカディアローリング:なだらかな丘」が無いと遊べないのは残念だった。
本家カスカディアでもシナリオチャレンジに挑み、全クリアした立場から言うと、カスカディアのチャレンジは後半で激鬼難易度になり何度も失敗を繰り返した。これ運ゲーじゃないか!と思いつつも、クリアできた時の達成感が半端ではなかったので、ローリングのシナリオチャレンジも単体で最後まで挑めるとなお嬉しかった。
まぁ、これは商業戦略とは相容れないことは理解しているが、シナリオチャレンジを途中まで遊んで面白かったためちょっと贅沢を言ってしまった。お許しいただけると幸いだ。
まとめ
以上、カスカディアローリングの特徴を見てきた。
・本作は2022年ドイツ年間ゲーム大賞の受賞作であるカスカディアのシリーズ作品である。
・ゲームの流れやプレイ感は本家とは大きく異なっている。特に動物は本家カスカディアでは主役だったのに本作ローリングではリソースのような扱いとなっており、大きな違いと感じる人も少なからずいると思われる。
・ただし、本作の4種のシートの構成は非常に巧妙。シートAからB、Cへと少しずつローリングのゲームの流れを学んでいき、最後のシートDで本家カスカディアのような二層パズルを目の当たりにする。動物は再び主役に返り咲く
・上記のような構成は1つのキャンペーンシナリオのようで非常に満足感が高い。
・しかし一方、上記の構成においてシートAはチュートリアルシートとなるため、Aだけ遊んで「あーこういう感じね」と見限られてしまう危険性も孕んでしまった。本作はシートA〜Dを全て通して遊ばないと真価は見えてこないと思われるが、Aのみで評価する人も生まれるのは本作の弱点。
・また、本作単体ではシナリオチャレンジが途中までしか遊べないのも残念。
・とはいえ、本作・カスカディアローリングの完成度は高く、リプレイ性もあり、満足のいく良作紙ペンとして仕上がっていると筆者は考える。
ぜひ皆様も一度手に取って遊んで欲しい。その際はシートA〜Dまで順番に全てを遊んでいただくことをお勧めしたい。
/post_image_d6e6559c-0e26-4fd1-97d2-a7a4b995692d.jpeg)
以上です!本家カスカディアも、本作・カスカディアローリングも好きなのでちょっと語りすぎてしまったかもしれません😅長文、乱文、失礼いたしました。
最後までお読みいただいた皆様、本当にありがとうございました。皆様の良きボドゲライフに少しでも役立てば何よりです^^
/item_8cfaeca9-59c1-415e-b4a5-80cc4c77c10c.png)
- 32興味あり
- 61経験あり
- 15お気に入り
- 85持ってる
18toyaさんの投稿
/post_image_921d24fa-9542-4f78-9217-1343f4b90b21.jpeg) レビューテイク・タイム【速報レビュー】難易度が高く一筋縄ではいかないが、成功した時の気持ちよ...約2ヶ月前の投稿
レビューテイク・タイム【速報レビュー】難易度が高く一筋縄ではいかないが、成功した時の気持ちよ...約2ヶ月前の投稿/post_image_389962db-3b4a-45aa-8f59-484cdaedfdad.jpeg) レビュークイズすごろく かぶーる【レビュー】抱腹絶倒!想像を越える面白さのバッティング系クイズすごろく...3ヶ月前の投稿
レビュークイズすごろく かぶーる【レビュー】抱腹絶倒!想像を越える面白さのバッティング系クイズすごろく...3ヶ月前の投稿/post_image_57bb2a70-b910-4261-8947-8b1461e5b641.jpeg) レビューキャッスルコンボ【レビュー】軽いプレイ感の中にゲーマ的思考が要求されるナイスな軽中量級...4ヶ月前の投稿
レビューキャッスルコンボ【レビュー】軽いプレイ感の中にゲーマ的思考が要求されるナイスな軽中量級...4ヶ月前の投稿/post_image_a02f6453-2839-4671-ab16-f155bd6b2ff8.jpeg) レビューディクシット適度に当てて適度に外して欲しい!ワード系ボードゲームの名作!【評価8/...5ヶ月前の投稿
レビューディクシット適度に当てて適度に外して欲しい!ワード系ボードゲームの名作!【評価8/...5ヶ月前の投稿/post_image_711021bd-8f0b-4c7d-ac21-395a652e697a.jpeg) レビューレジスタンス:アヴァロン脱落のない正体隠匿。人狼ゲームが好きな方には太鼓判でオススメ!【評価8...6ヶ月前の投稿
レビューレジスタンス:アヴァロン脱落のない正体隠匿。人狼ゲームが好きな方には太鼓判でオススメ!【評価8...6ヶ月前の投稿/picture_0d65618c-968e-41ea-abc4-e8725cfcbadd.webp) レビュー指輪物語:運命の旅【ロングレビュー】パンデミックのシステムを核にしながら大胆なアレンジで...7ヶ月前の投稿
レビュー指輪物語:運命の旅【ロングレビュー】パンデミックのシステムを核にしながら大胆なアレンジで...7ヶ月前の投稿/post_image_796a1a7b-8578-421e-9b88-84c1f687fd01.jpeg) レビューファウナ【レビュー】知ってるようで意外と知らない動物トリビア!好きな人なら長〜...8ヶ月前の投稿
レビューファウナ【レビュー】知ってるようで意外と知らない動物トリビア!好きな人なら長〜...8ヶ月前の投稿/picture_cfc036ed-ac69-4ff8-bb9b-733c6ef0ff8e.webp) レビューオラニエンブルガー運河【レビュー】経路と建物の配置もアクション順も大事!あちらを立てればこち...9ヶ月前の投稿
レビューオラニエンブルガー運河【レビュー】経路と建物の配置もアクション順も大事!あちらを立てればこち...9ヶ月前の投稿/picture_cfc036ed-ac69-4ff8-bb9b-733c6ef0ff8e.webp) ルール/インストオラニエンブルガー運河本作を遊ぶときに、引っ掛かりなく気持ちよく遊べるよう、ちょっとしたポイ...9ヶ月前の投稿
ルール/インストオラニエンブルガー運河本作を遊ぶときに、引っ掛かりなく気持ちよく遊べるよう、ちょっとしたポイ...9ヶ月前の投稿/picture_974f8715-cf1d-4eba-8158-502a9a8f5d20.webp) レビューブルゴーニュの城: スペシャルエディション【レビュー】もはや家宝級!究極のブルゴーニュはここにある!【評価9.5...11ヶ月前の投稿
レビューブルゴーニュの城: スペシャルエディション【レビュー】もはや家宝級!究極のブルゴーニュはここにある!【評価9.5...11ヶ月前の投稿/rummikub2.jpg) レビューラミィキューブ【レビュー】手牌をいかに場に出せるか、頭は常にフル回転!スリリングな頭...11ヶ月前の投稿
レビューラミィキューブ【レビュー】手牌をいかに場に出せるか、頭は常にフル回転!スリリングな頭...11ヶ月前の投稿/picture_73509393-212f-418b-a8ad-6e3066ba6939.webp) レビューメソス【レビュー】プレイ時間も悩み具合も丁度いい!通も楽しめるオープンドラフ...約1年前の投稿
レビューメソス【レビュー】プレイ時間も悩み具合も丁度いい!通も楽しめるオープンドラフ...約1年前の投稿
会員の新しい投稿
/post_image_c71475a4-77db-4fe0-bbdd-72e1a3047408.png) レビューナインティ・ナインバリアントを入れて、4人で遊ぶにはちょっと多いかもしれません。1ゲーム...約2時間前by atckt
レビューナインティ・ナインバリアントを入れて、4人で遊ぶにはちょっと多いかもしれません。1ゲーム...約2時間前by atckt/post_image_bdf3ac96-7a2d-498b-bde6-81176520217c.png) レビューグラシアス発売された当初に遊んでから、約20年ぶりに遊びました。割とソリッド気味...約2時間前by atckt
レビューグラシアス発売された当初に遊んでから、約20年ぶりに遊びました。割とソリッド気味...約2時間前by atckt/post_image_dce5936f-33e4-4059-971d-3c900a39e264.png) レビューリッチモンド貴婦人割とクラシックな競りゲームです。ゲーム中チップが4回補充されるのですが...約2時間前by atckt
レビューリッチモンド貴婦人割とクラシックな競りゲームです。ゲーム中チップが4回補充されるのですが...約2時間前by atckt/post_image_06163d2f-bd35-40b0-a564-66f50ca52320.png) レビューシルバー&ゴールド ピラミッド最近出た好きな上ペンです。カードに直接書きます。基本的にはパズルゲーム...約2時間前by atckt
レビューシルバー&ゴールド ピラミッド最近出た好きな上ペンです。カードに直接書きます。基本的にはパズルゲーム...約2時間前by atckt/post_image_c2ce4cb6-f665-4085-8429-051516bb38f4.png) レビューオール・ザ・ウェイ・ホーム1色の豚を担当しない、レースゲームです。移動した豚をトップにできれば得...約2時間前by atckt
レビューオール・ザ・ウェイ・ホーム1色の豚を担当しない、レースゲームです。移動した豚をトップにできれば得...約2時間前by atckt/post_image_c36e307e-2a2d-4c01-9f25-0a25908c9eba.png) レビューダンダンダイス言葉をうまく探し当てる、推測型の協力ゲーム。ダイスを振って、キューブを...約3時間前by atckt
レビューダンダンダイス言葉をうまく探し当てる、推測型の協力ゲーム。ダイスを振って、キューブを...約3時間前by atckt/picture_27194eb8-8011-44b7-b919-4c306468a22b.jpg) レビューエスケイプ・プラン5人プレイ。インスト1時間プレイ3時間。初ラセルダゲームでしたが、噂に...1日前by oliber
レビューエスケイプ・プラン5人プレイ。インスト1時間プレイ3時間。初ラセルダゲームでしたが、噂に...1日前by oliber/picture_605b3e11-2ed6-4219-b83c-026b6bfdcaf5.jpg) ルール/インストプロジェクト:エリートProject: ELITEでは、プレイヤーはELITE部隊の一員とな...1日前by ゴーダ
ルール/インストプロジェクト:エリートProject: ELITEでは、プレイヤーはELITE部隊の一員とな...1日前by ゴーダ/picture_288328d1-7104-426e-b2c6-7ff4f03f3be4.webp) レビューリフトフォース:ビヨンド(拡張)5/5点リフトフォース拡張。新たなエレメンタルが8種類増えておりソロプ...1日前by ワタル
レビューリフトフォース:ビヨンド(拡張)5/5点リフトフォース拡張。新たなエレメンタルが8種類増えておりソロプ...1日前by ワタル/post_image_8af545b5-4074-456b-add0-6a1854a92951.jpeg) レビューチケットトゥライド:ドイツ列車を配置し自分の路線を作っていくゲーム友人たちと4人でプレイしました...1日前by レモネード
レビューチケットトゥライド:ドイツ列車を配置し自分の路線を作っていくゲーム友人たちと4人でプレイしました...1日前by レモネード/post_image_c7d70342-1f7d-4821-978d-69703474450c.jpg) レビュー白と黒でトリテ 明朝&ゴシック白黒の1-7の49枚を使用。ビッド式のマストフォローのトリテですがフォ...2日前by 七盤のハムさん
レビュー白と黒でトリテ 明朝&ゴシック白黒の1-7の49枚を使用。ビッド式のマストフォローのトリテですがフォ...2日前by 七盤のハムさん/picture_4ab8b23e-8069-4860-bf2d-996fa5579d2a.webp) レビューチューリップバブル素敵なアートワークとコンポーネントに惹かれ購入しました。 上下する相場...2日前by じん
レビューチューリップバブル素敵なアートワークとコンポーネントに惹かれ購入しました。 上下する相場...2日前by じん

/advertise/og_anniversary_2026.png)

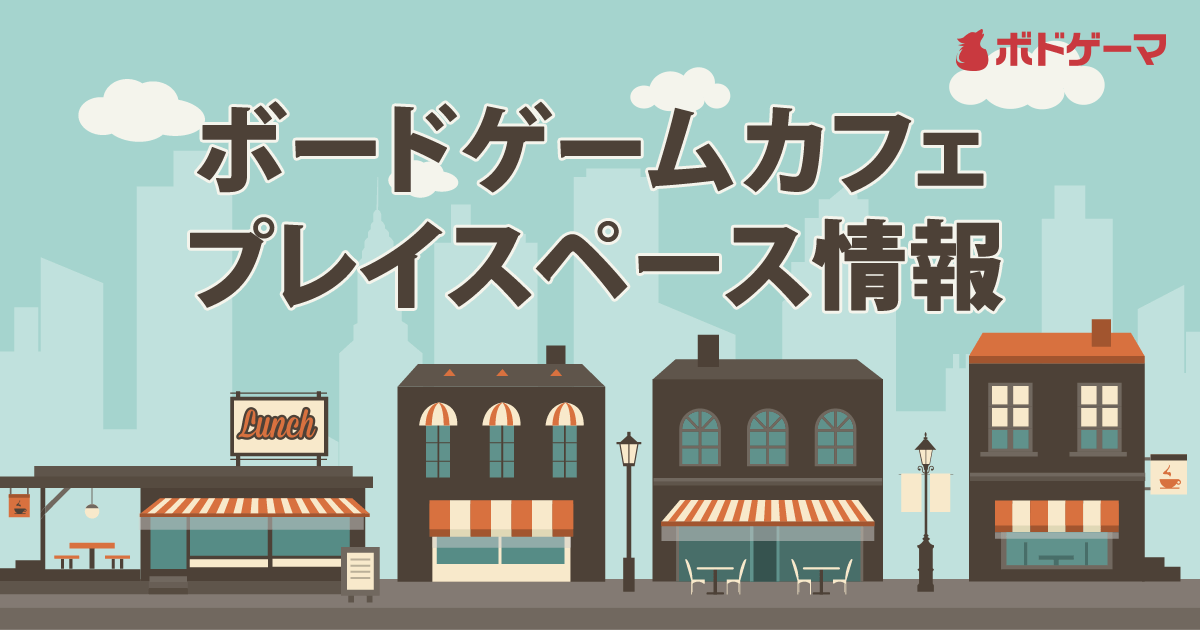
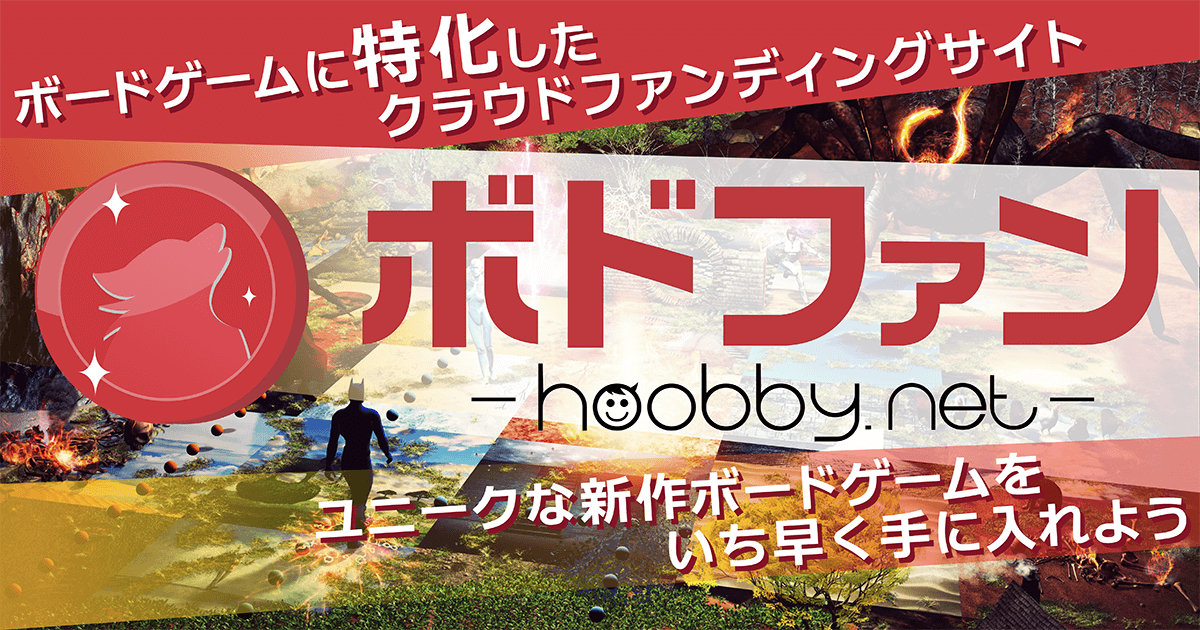
/picture_4d7f4962-4abc-4937-8245-f8f32042948a.png)
/picture_50ea999e-587f-460f-89c0-e9694e82b891.jpeg)
/picture_69e2054b-aeb4-4e40-9b0c-6f25ffda1a97.webp)
/picture_4ab8b23e-8069-4860-bf2d-996fa5579d2a.webp)
/picture_ea6097d8-42fe-42b6-88e1-a105946c73e6.jpg)
/picture_a08f71bf-b0b5-4d5e-bac8-0798ef06c1ff.jpg)
/picture_99a21a4a-fe35-442a-b031-44b5d74a53c9.jpg)
/picture_1c2eccdc-1d89-46e7-8df7-d5bf7d192506.webp)
/picture_796b50fe-5d91-4a30-a898-4affe4fdafeb.jpg)
/noimage_game.png)
/picture_27194eb8-8011-44b7-b919-4c306468a22b.jpg)
/picture_e47d4ebe-9415-4a85-870e-a06c24ccca18.jpeg)
/picture_b43be6eb-3dea-4a9c-a245-0905e41ebf44.jpg)
/picture_616880d1-1b0a-49cc-a12f-e4273b5cbbdf.png)
/picture_e42591d0-2435-474c-9026-98f6dbdbb10f.jpg)
/picture_fc58fd1f-fc81-4eff-ba85-10aef10b30f5.jpeg)
/picture_43d8f76e-0287-4c75-8de4-bc5c2119e801.jpg)
/picture_db276ec7-9f43-43c1-a42a-c1d8d344399e.jpg)
/picture_8f3e5eeb-c6c2-43c4-a54a-6270db9358e1.jpg)
/picture_f3a621ab-ce1e-4fd9-afc5-a6c86b3c3da7.jpeg)
/picture_c56edf2c-3f61-478b-8e85-24fc268e2c84.jpg)
/die-siedler-von-catan_thumb_1.bing_en.jpg)
/dominion_thumb_37.bing_en.jpg)
/picture_d2713af1-45bb-4f3f-bfcb-3a40d059c061.jpg)
/picture_54e881df-ed6a-4865-8f08-290676842639.jpg)
/picture_223cfea0-36a5-4041-912f-1bf086330158.jpg)
/picture_3a2dc9ac-11d9-4ace-9556-6eb1bf6f180b.jpg)
/picture_aa1601fa-59ef-497c-8510-6ae7e1d530fc.jpg)
/picture_f1858e77-7867-4d37-9b90-67cb9548d22e.jpg)
/picture_868b38ad-f427-40a0-b4d1-645c78fc204b.jpg)
/picture_836d5f4d-8cbd-4c6c-b59f-45d43654e0da.jpg)
/picture_cf725a25-82dd-4dae-bd2f-68755461b0a5.jpg)
/agricola-2.jpg)
/7-wonders3.jpg)
/picture_72104e44-09b6-4df7-8d81-809c3bfbfff3.jpg)
/picture_71c7f15a-a731-46f1-9afb-d16c0617f3e2.webp)
/picture_63f5a7ec-b69a-407e-979d-281922287a84.jpg)
