- 2人~4人
- 60分~90分
- 10歳~
馬高月向こねこさんのレビュー
新潟県の信濃川では、新石器時代、いわゆる縄文時代に作られたと推測されている『火焔型土器』と呼ばれる土器が、上流から河口まで約130kmの流域において出土されているという。このゲームでは、その火焔型土器が作られた縄文時代を舞台に一族の長となり、土器を作り、犬と狩りを行い、次の年への繁栄を目指して四季を過ごしていく。
プレイ人数は2~4人、記載プレイ時間は60~90分、インスト込みの実プレイ時間は120分程。
(感想部において余計な長文を書き上げてしまったことをお許し下さい。それだけこのゲームに対して言いたいことが沢山あるのです)
/post_image_8c0621c3-28c6-4ce4-a0e7-6e9805812f83.jpg)
自分の手番にできることは家族コマの配置と資源獲得(写真左側)となる。更に、それに伴って探索トラック(写真右側)上の探索コマの移動と効果の解決、状況に応じて土器や建物の制作が行える。順を追って簡単に説明していく。
/post_image_1e304bcf-aa4e-4cd6-80dc-69e578d669ba.jpg)
家族コマの配置と資源獲得では、盤面左側の白い円が描かれた箇所に、円の数だけ駒を置くことで資源を得ることができる。資源は木材(木のシンボル)、粘土(灰色の四角形シンボル)、霊感(火のシンボル)の3種類。それに加え、狩りによる動物チップの獲得や、探索トラックの追加移動、そのラウンドのみで使用できる追加の犬コマの獲得なども行える。
さて、いきなり犬コマというコマが出てきたが、これは何か。縄文時代において、既に犬は人間と寄り添って暮らす存在となっていたと推測されている。生活域において共に暮らしていた形跡があり、人間と一緒に埋葬されていた痕跡もあるらしい。つまりは犬も家族であり、要するにワーカーとして使用できる。ただし、結局は犬なので、家族コマを最低1つ組み合わせる+犬コマは家族コマより多くできない点は注意が必要だ。
家族コマ、犬コマは、プレイヤーカラーのものとは別に白色のものも存在する。これは上記の盤面へのコマの配置、あるいは後述する建物の制作時に獲得できる一時的なワーカーで、ラウンド終了時にはコマ置き場に返さなければいけない。
コマの配置が終わり配置箇所の処理を終えた後、盤面右側の探索コマの移動を行う。盤面に配置したコマの数だけ、探索コマが探索トラックを時計回りに動いていく。動いた先、探索コマが止まったタイル上に描かれた効果を実行する。資源の獲得が主だが、タイルによっては資源の変換、狩りで魚を獲得、白犬コマの獲得等の効果もある。
この探索コマの移動があるため、上述の家族コマの配置時に(少ないコマでも同数の資源が獲得できるのにも関わらず)わざと多くのコマを配置して、探索コマの歩数を稼ぐという動きが視野に入ってくる。単純にタイルに描かれた効果を先取りしたいからという理由はもちろん、次に説明する土器や建物の制作や、ラウンド終了時のボーナスにも関わるため、配置コマの個数で歩数を稼ぐ(あるいは明確に刻んでいく)のに明確な意味が生じているのだ。
探索コマの移動後、探索トラックの四隅(オレンジ色の部分=制作アイコン)を通過していた場合は、土器や建物の制作が行える。所持している資源を支払って、ディスプレイされている土器を制作(=自分の手元に持ってきて得点化)する、または制作ボード上(写真撮り忘れ)にある4種の建物のうち1つのレベルを向上させることができる。
ディスプレイされている土器の作成は単純で、資源を支払い土器タイルを手元に持ってくる。タイル左下に描かれている白い数字がタイルの素点で、右の小さな数字はラウンド終了時に追加で得られるボーナス点(後述)となる。
建物のレベル向上は、家族コマの増加、犬コマの増加、土器制作時の資源減少、コマを置けるアクションスペースの増加、という4種類から好きなもののレベルを上げることができる。
土器で得点を得るか、後の展開を見越して建物のレベルを上げるかが悩ましいところではあるが、探索コマが制作アイコンを通過しないことにはこれらのアクションを行うことはできない(タイル効果による例外あり)。回数が限られる重要なアクションなので、慎重に選択をしたいところだ。
時計回りで順にコマを配置していき、全プレイヤーがコマを配置できなくなった(=全員がパスをした)タイミングでラウンドが終了する。ラウンド終了時の処理として、探索トラックの順位でのボーナス(翡翠チップ)の獲得、各資源の家族コマ配置最多プレイヤーへのボーナス(木の実コマ)の獲得、所持している木の実コマの調理(土器タイルへの木の実コマの配置)を行う。すべての処理が完了した後、探索トラックの所定位置のタイル更新、家族コマの回収等のクリーンアップ処理を行い、次の季節(=ラウンド)へと移行する。これを4ラウンド行うとゲームが終了する。
/post_image_18937c10-5f62-4085-9d76-3cc0f384d09e.jpg)
ゲーム終了時のボーナスは全部で5種類あり、
1.狩った動物の種類(1種2点~6種30点)
2.最終ラウンドで次ラウンドスタートプレイヤーの権利を得た場合2点
3.土器に置いてある木の実コマの数(1位10点、2位4点)
4.ゲーム中に獲得した翡翠チップに描かれた点数の合計(非公開情報)
5.余った資源5種を1点に変換
となっている。これらを最終ラウンド終了時の得点(土器や建物制作時に発生した得点)に加算したものが最終得点となる。最も得点が高かったプレイヤーの一族が、縄文時代の一年をもっとも充実して過ごせたということになる。
/post_image_6adf3e5a-0f75-4740-80ba-9e15b1da92e9.jpg)
長々とシステムについて書いてしまった。ここからはプレイした感想に移りたいと思う。
最初に述べておきたいのは、このアカデミックな内容のテーマを、ここまで落とし込んで、練り込んで、ゲーマーズゲームに仕立て上げたデザイナーの手腕に驚いたという点だ。
これは個人的な、しかも少々黴臭い(同人ボドゲ界隈の動向を数年単位で観測していない人間の)感覚に基づく偏見であるが、こういったアカデミックなテーマを持つゲームは、ゲームとしての練度(システムの練度)が低いと考えていた。過去にゲームマーケットで出展者の卓を見て回っていた時に、〇〇研究会や〇〇大学といったネームバリューと、『我々の研究結果をボードゲームにしました!』という売り込み文句に惹かれ立ち寄ってみたことが何度かあった。だが、ゲームのシステムとしては(言葉選びが悪いことを許して欲しいが)陳腐であると言わざるを得なかった、という事が多々あったのだ(蓋を開けてみたら神経衰弱+αだったとか、クイズだったとか…)。
正直に話すと、この作品も(ゲーム内容を全く知らないにも関わらず)同様であると断じ、これを購入すると決めたボードゲーム会の友人に対して淡い憐憫の念を抱いてしまっていた。
しかし、ゲームマーケット開催から2週間後のゲーム会で、友人はこのゲームを絶賛していた。ゲームに関しては確かな目を持っているのは分かっていたので、何かがあるのだろうとこの時点で感じた。同時に、チラホラとX(Twitter)上でもこのゲームの感想を見るようになった。何かが自分の認識とズレている(そして恐らく自分が基準点からズレた側にいる)と感じた。
1ヶ月が経過した今日、友人はこのゲームを持ってきた。そして、酒を飲みながらワンちゃんを撫でるゲームで、盤上でフラッフラになってる自分に「そのゲームあと15分もあれば終わるよね? 席空けて待ってるから、終わったらすぐにこっちの卓に来てね!」と誘ってくれたのだった。
確かに2週間前の絶賛を聞いた際に「んだらば次やってみんべよ?」とは言った。だが折しも時刻は正午過ぎ。会場近所の居酒屋で、昼飯に大盛りのネギトロ丼を食べる算段を立てていた身としては、こうあれよあれよと着卓を義務付けられてしまったことに困惑を覚えていた。が、一方でボードゲーマーの嗅覚が『これを逃したらプレイできない』と嗅ぎ取ったのと、『そこまで誘われちゃぁ断れねぇよ?』という思いが相まり、卓へと向かったのだった。着席して開口一番友人に『ネギトロ丼食べる楽しみを潰したんだから、相応のものがあるんだよねぇ?(フシャァァ』と威嚇した。
インストが終わり、1手目を始める前、「ぼくねぇ、このゲームねぇ、だいすきだとおもう」と言った。
手のひらクルックルどころか、ぎゅるるんドリル状態である。
インストの時点で、面白いと分かったのだった。自分が持っていた偏見が全て吹き飛んだのだった。自分が如何に矮小な視野に立っていたかを思い知らされたのだった。そして、これからのゲーム体験に胸が高鳴ったのだった。
それからの約1時間半、特に後半は、集中力を切らさず脇目も振らず、自分が思い浮かべた最善手をその通り実行することのみに注力した。昼食代わりに10秒チャージしたゼリータイプ栄養補助食品ラムネ味と、某エネルギードリンク味ラムネで摂取したブドウ糖を、脳が息をするかのごとく消費していくのが分かった。とにかく馬高を、火焔型土器を作る。それだけを狙ってアクションを行った。というのも、他のプレイヤーが土器制作もそこそこに狩猟方面に走ってしまい、最後のボーナスで捲くられる可能性を常に考慮する必要が発生したからだ。いわば追われるような形でのプレイ。なるほど、追われる者の方が辛いという言葉が身にしみる。
ゲーム中にボーナスの翡翠チップを獲得した。最初、この緑色のチップは緑黄色野菜か何かか?と思ったものの、ルールブックの文頭に新潟県信濃川とあったのを思い出し、流域は確か水害が多いことから『厭い川』と呼ばれていたのではなかったか?と思い出し、更に翡翠が名産であったと思い至った(実はこれは後で調べたところ、信濃川ではなく同県にある姫川の別名であった。自分の知識の浅さを恥じたいところ。…まぁそれはさておき)こうした細かい部分にまで徹底してテーマを織り込んできている辺り、このゲームの練り込みの高さを感じた。
序盤こそ低コスト土器に手を出したものの、2ラウンド目あたりで『筋』――火焔型土器制作特化という道筋が見えた。以降、『我は森の犬(白犬コマ)と共に歩むもの…』と自分に言い聞かせ、建物のレベル向上に関しては家族コマと犬コマの増加、土器制作資源減少には一切手を出さず、追加アクションの開放だけを行った。結果、2ラウンド目の時点でラウンドごとに霊感2を独占入手できる状態を確保。その後は制作アイコン通過時に木材を霊感に変換等で、霊感の補給と在庫を常に意識しつつ、その他の資源獲得と探索を行った。最終的に、火焔型土器を4つ制作し、それのみで66点を得た。更にそれに加え、他要素得点や各種終了時ボーナス等々を加算し、最終得点は134点。狩猟ボーナスで30点を得た2位との点差は13点。中得点域の土器1個分と、ギリギリの勝利となった。
久々に『ボードゲームで脳を酷使する』という、半ば自傷的とも言えるボードゲーマー特有の満足感へと至れた。事実、ゲームが終了して勝利が確定した瞬間、身体が急に重くなり、テーブルに突っ伏した。それほどまでに夢中になった。「んふふふふー」と恍惚に浸りつつ、テーブルに突っ伏して力無く笑うこのねこを、見てもどうかドン引かないで欲しい。このゲームを本気でプレイすれば、恐らくあなたもそうなるのだから。
※追記:なお翌日犬コマの取り扱いでのルールミスが発覚し、上記ゲームはノーゲーム、この勝利は無効となりました。えへっ☆(吐血)
/post_image_bcc13ebf-8a79-452e-82dd-ef83ebe73996.jpg)
縄文時代と火焔型土器という類を見ないアカデミックなテーマと、これもまた類を見ない独特なワーカープレイスメント+可変ロンデルシステム。システム単品で見ると各々普遍的なギミックであることは否めない。しかし、これらが合わさったこと、ロンデルのマスをタイルにして可変性(リプレイ性)を高めたことは、このゲームを本格的な、そして何度も遊べる中級ボードゲームにしたかったのだという明確な意図を感じた。そして特筆すべきは、上述の通り探索コマの歩数を調整するために、『あえて必要最低限以上のワーカーを置く』というプレイングを許容する自由度を残した点。この調整には唸ってしまった(この文を書きながらデザイナーズノートを読んで、テストプレイヤーがこの動きをしていることから、システムとしてそれを制限しない方向に舵を切ったあたり、デザイナーとしての観察力とバランス感覚が優れているなと感じた)。
テーマだから土器制作をやって欲しいという想いがにじみ出ているのを感じつつも、狩猟によるボーナスも決して侮れないという、得点源を1つに絞らなかった点も評価したい(そして、縄文時代は狩猟採取経済から水耕生産経済への過渡期だったと考え、これらの得点源のバランスにテーマ的な重みも加わっているだろう想像すると、そこも併せて評価したくなる)。そして翡翠や木の実といった小さな得点源も、後々馬鹿にできない得点をもたらしてくれる点も忘れてはならない。総じてどの部分も腐ること無く、上手く伸ばせればちゃんと伸び、プレイヤー間インタラクションによるストレスもゲームの楽しさを損なうレベルでは感じず、自分の手をどんどん進めていける楽しさが出ていると思った。
このゲームを作るにあたって、周りの協力体制が整っていたのも、プレイしてみるとよく分かる。土器タイルに使われている土器の写真は、新潟県の博物館から提供された実物の写真を使用しているとのこと。また、ルールブック巻末には博物館研究員のコラムが1ページ丸々使って記載されている。なぜ信濃川流域が『火焔土器の国』と呼ばれているかを簡潔に説明しつつも、書かれている内容で更なる知識欲をくすぐられ、ゲームプレイ後に読むと縄文時代や土器について自分でも調べてみたくなるのだ。こういったゲームプレイをきっかけに、『未知の領域への最初の一歩』を踏み出させてくれる作品というのは、とてもありがたく、貴重な存在であると思う。
更には(また偏見を引っ張り出すのだけれども)こうしたテーマで、しっかりとシステムを練り上げることができた作品として、新たな地平を切り開いた感がある。特異点と言っても良いのではないだろうか。この作品を期に、こういった作品が徐々に増えていく流れができるのだとしたら、このゲームの存在意義は計り知れないものになるだろう。
変に大局的な見方をして色々と言葉をこね回してしまっているが、要するに評価としては、
『これはめちゃくちゃいいゲーム』
という一言に尽きるのである。
機会があるのであれば、是非プレイしてみて、縄文時代と火焔型土器に想いを馳せてみてはどうだろうか。
プレイしてる最中に「わかーってるのはー、どきのむねむねー、どきのむねむねだけー♪(ハイロウズの『胸がドキドキ』の替え歌)」って歌ってたら、「ねぇこれあと1時間半も聞き続けなきゃいけないの…?」って怪訝な顔するのやめてよぉ。ねぇ。集中力切らすようなことして悪かったらからさぁ。ほんと、ごめんて。
あ、あと久々に2時間くらいプレイしたゲームで勝ったからって、『勝てたゲームはいいゲーム』心理で高評価にしてるわけじゃないからね! ほんとだからね!!
- 155興味あり
- 345経験あり
- 107お気に入り
- 235持ってる
月向こねこさんの投稿
/picture_6a57fa8e-39b5-4ee6-bab4-eaab3e618bae.webp) レビューカバンゴアフリカ大陸に存在する、世界最大の自然保護区『カバンゴ・ザンベジ国際保...1年以上前の投稿
レビューカバンゴアフリカ大陸に存在する、世界最大の自然保護区『カバンゴ・ザンベジ国際保...1年以上前の投稿/picture_33b8c2a1-b290-4478-a2fc-f268c6fc3a0c.webp) レビューアンダーグローブ3億年以上もの間、樹木は菌類と共生関係を築いてきた。樹木は菌類が土壌か...1年以上前の投稿
レビューアンダーグローブ3億年以上もの間、樹木は菌類と共生関係を築いてきた。樹木は菌類が土壌か...1年以上前の投稿/picture_d3914b91-3b51-4dc0-a95f-32ea0f491cae.webp) レビューノクターン月夜の森を舞台に、狐の魔術師たちが呪文を唱え、魔法のアイテムを争奪する...1年以上前の投稿
レビューノクターン月夜の森を舞台に、狐の魔術師たちが呪文を唱え、魔法のアイテムを争奪する...1年以上前の投稿/picture_f5ed625d-337d-4326-b373-e9e98d4bb5bc.webp) レビュービラボングビラボング(オーストラリアで使われる『川から枝分かれした行き止まりの水...2年弱前の投稿
レビュービラボングビラボング(オーストラリアで使われる『川から枝分かれした行き止まりの水...2年弱前の投稿/picture_40a1b4af-2850-4c14-8b86-d9e3b0d6ea6e.jpeg) レビューホイアン / ファイフォ16~17世紀、ベトナムの港町ホイアン。商人組合のリーダーとなったプレ...2年弱前の投稿
レビューホイアン / ファイフォ16~17世紀、ベトナムの港町ホイアン。商人組合のリーダーとなったプレ...2年弱前の投稿/post_image_6849a719-1fec-4f37-a226-058eed4f0b12.jpg) レビューアートソサエティ絵画をコレクションするコレクターになって、オークションで絵画を落札し、...2年弱前の投稿
レビューアートソサエティ絵画をコレクションするコレクターになって、オークションで絵画を落札し、...2年弱前の投稿/post_image_501692f2-d1e2-44fe-9648-359251732f7f.jpg) レビューマッチオブザセンチュリー1972年の世界チェス選手権における世紀の対決、ソ連代表ボリス・スパス...約2年前の投稿
レビューマッチオブザセンチュリー1972年の世界チェス選手権における世紀の対決、ソ連代表ボリス・スパス...約2年前の投稿/post_image_dea7bf44-6c65-44e4-af7b-9e5a767d0a74.jpg) レビューフィット・トゥ・プリントプレイヤーは新聞社の編集者となって、ネタをかき集めて自分が担当する紙面...約2年前の投稿
レビューフィット・トゥ・プリントプレイヤーは新聞社の編集者となって、ネタをかき集めて自分が担当する紙面...約2年前の投稿/picture_47d31ca3-fc00-4bfa-b84d-6a72f054f444.webp) レビューフーディーフォレストライナー・クニツィア教授の『Too Many Cooks(料理人が多す...約2年前の投稿
レビューフーディーフォレストライナー・クニツィア教授の『Too Many Cooks(料理人が多す...約2年前の投稿/post_image_6b08884e-6115-4c98-9dbc-7f9f6006bd2b.jpg) レビューレッドウッドプレイヤーは動物写真家となって、盤面の自駒を移動させて動物や景色を撮影...約2年前の投稿
レビューレッドウッドプレイヤーは動物写真家となって、盤面の自駒を移動させて動物や景色を撮影...約2年前の投稿/post_image_4c704d11-fe7d-4692-a208-e4286f304bcc.jpg) レビューメドウプレイヤーは自然観察者になって、周りにある自然を観察して動植物の植生や...約2年前の投稿
レビューメドウプレイヤーは自然観察者になって、周りにある自然を観察して動植物の植生や...約2年前の投稿
会員の新しい投稿
/picture_a22bae21-23ca-4985-b721-c46669c4ccf0.jpg) レビュー坊茶 スタンダード版シンプルでそこそこ楽しい。16分前by ジョジョ
レビュー坊茶 スタンダード版シンプルでそこそこ楽しい。16分前by ジョジョ/picture_32e8aad4-9c7e-4c5e-8ffc-2655e401e62d.jpg) レビューブラフ / ライアーズダイス名前の通りブラフゲーム。全体に何の目がどれくらいあるかを予想する。ぴっ...19分前by ジョジョ
レビューブラフ / ライアーズダイス名前の通りブラフゲーム。全体に何の目がどれくらいあるかを予想する。ぴっ...19分前by ジョジョ/picture_2ae73f29-466c-43c8-b8c6-e9e64060ab6f.webp) レビュールアー:ディープ・ウォーターズルアーの拡張。一回で釣り上げることができない耐える魚が登場。バリエーシ...21分前by ジョジョ
レビュールアー:ディープ・ウォーターズルアーの拡張。一回で釣り上げることができない耐える魚が登場。バリエーシ...21分前by ジョジョ/picture_fa3f965e-5064-4771-a9b9-ebd9773c0ad1.webp) レビュールアー魚釣りがテーマのダイスゲーム。ダイスの数が少ない人からダイスを振れるの...22分前by ジョジョ
レビュールアー魚釣りがテーマのダイスゲーム。ダイスの数が少ない人からダイスを振れるの...22分前by ジョジョ/picture_7c74e833-c715-4670-959c-b500f4253259.jpeg) レビューみんなでぽんこつペイント画力がなくても遊べるゲーム。うまく伝えながらも画数を少なくするのがポイ...24分前by ジョジョ
レビューみんなでぽんこつペイント画力がなくても遊べるゲーム。うまく伝えながらも画数を少なくするのがポイ...24分前by ジョジョ/post_image_156303d9-ed4b-4cec-946a-09f3b8b7d5ed.jpeg) レビューライフ・オブ・ジ・アマゾニア地形タイルを配置し、動物たちを効率的に並べていくボードゲーム「カスカデ...37分前by アッキーノ
レビューライフ・オブ・ジ・アマゾニア地形タイルを配置し、動物たちを効率的に並べていくボードゲーム「カスカデ...37分前by アッキーノ/picture_2425fb29-71f5-4276-98e0-f61b8cd9a5d8.webp) レビューアービフィアービフィは、自分の政党の議員を各委員会に派遣し、そこで得た影響力を使...約1時間前by KEITA
レビューアービフィアービフィは、自分の政党の議員を各委員会に派遣し、そこで得た影響力を使...約1時間前by KEITA/picture_b767c2e5-af1f-4591-8350-4bf60a82c536.jpg) レビューそういうお前はどうなんだ?大喜利的なゲームだが、世界観への導入が甘く、内容もあまりにプレイヤー任...約4時間前by ご隠居
レビューそういうお前はどうなんだ?大喜利的なゲームだが、世界観への導入が甘く、内容もあまりにプレイヤー任...約4時間前by ご隠居/picture_a6f4e2bf-ed6a-43e3-9a0b-ffad940c3588.jpg) レビューこのエピローグは変わらない4人でプレイしましたゲームの流れとしては物語のエピローグ、経過時間、エ...約13時間前by saito
レビューこのエピローグは変わらない4人でプレイしましたゲームの流れとしては物語のエピローグ、経過時間、エ...約13時間前by saito/picture_c4508d08-437f-4670-bb5b-518f8472c712.webp) レビュータクタBGAで1回プレイして即実物を購入しました。(英語版)ウボンゴ、プロジ...約13時間前by タカミネコウヘイ
レビュータクタBGAで1回プレイして即実物を購入しました。(英語版)ウボンゴ、プロジ...約13時間前by タカミネコウヘイ/post_image_c71475a4-77db-4fe0-bbdd-72e1a3047408.png) レビューナインティ・ナインバリアントを入れて、4人で遊ぶにはちょっと多いかもしれません。1ゲーム...約15時間前by atckt
レビューナインティ・ナインバリアントを入れて、4人で遊ぶにはちょっと多いかもしれません。1ゲーム...約15時間前by atckt/post_image_bdf3ac96-7a2d-498b-bde6-81176520217c.png) レビューグラシアス発売された当初に遊んでから、約20年ぶりに遊びました。割とソリッド気味...約16時間前by atckt
レビューグラシアス発売された当初に遊んでから、約20年ぶりに遊びました。割とソリッド気味...約16時間前by atckt

/advertise/og_anniversary_2026.png)

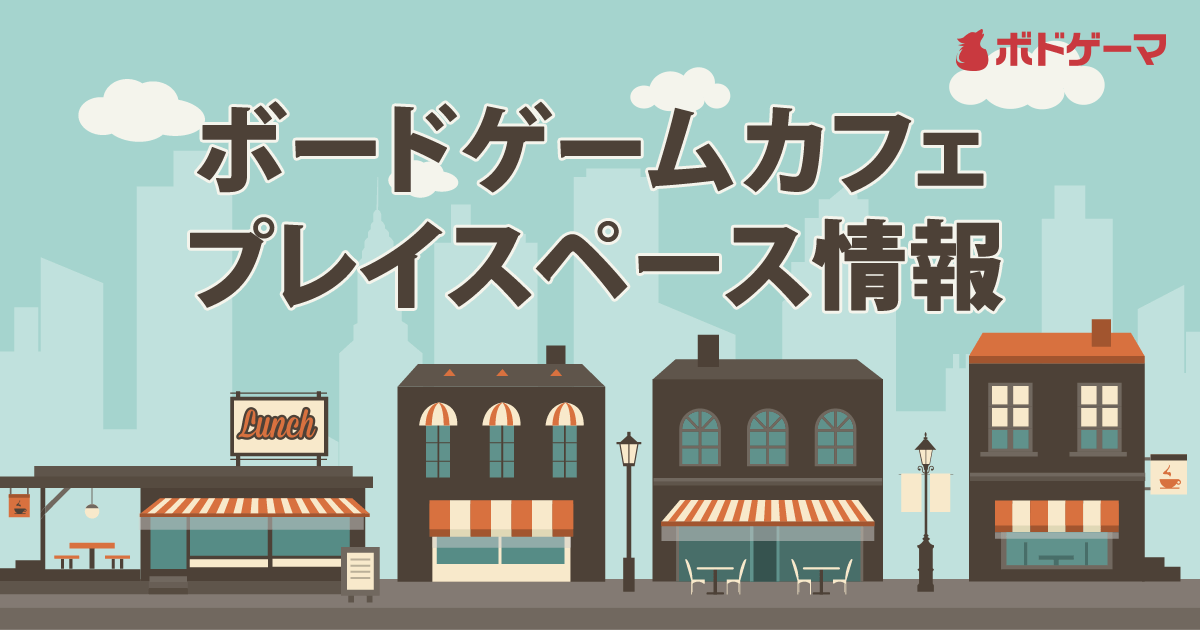
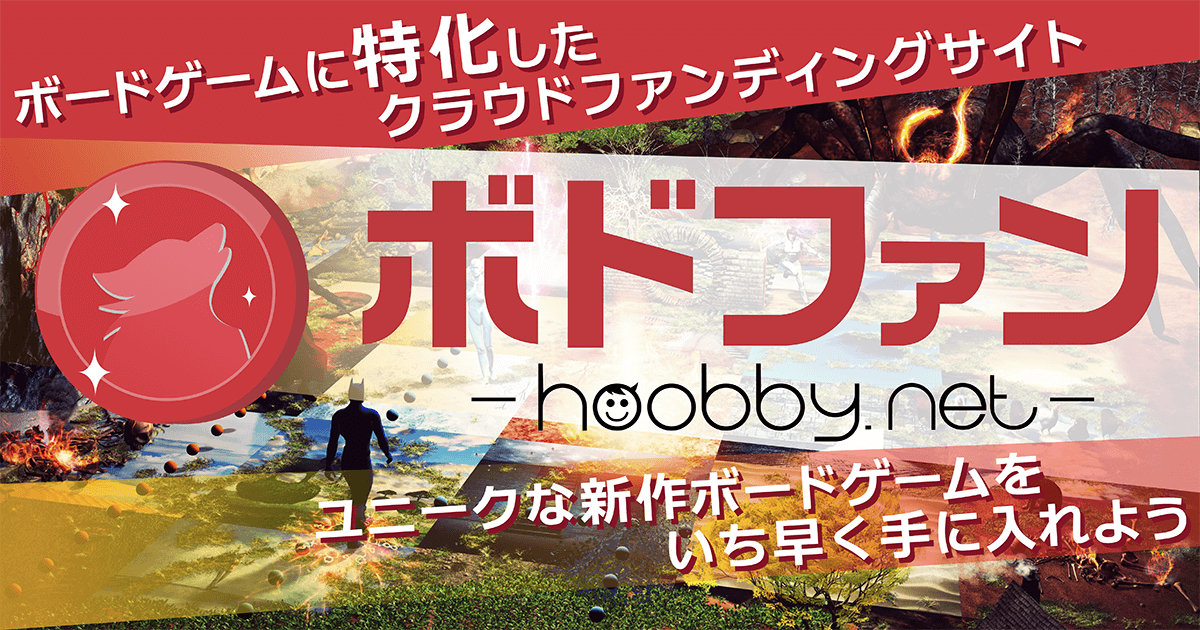
/picture_50ea999e-587f-460f-89c0-e9694e82b891.jpeg)
/picture_27194eb8-8011-44b7-b919-4c306468a22b.jpg)
/picture_485f7e86-a899-4768-8e71-26445b0cbbdb.jpg)
/picture_fc5c7442-37e4-43c0-b51b-c3c66ccd0a86.JPG)
/picture_ea6097d8-42fe-42b6-88e1-a105946c73e6.jpg)
/picture_4ab8b23e-8069-4860-bf2d-996fa5579d2a.webp)
/picture_e1ef2684-3c81-4255-933e-60c5210095fb.jpg)
/noimage_game.png)
/picture_f3a621ab-ce1e-4fd9-afc5-a6c86b3c3da7.jpeg)
/picture_a08f71bf-b0b5-4d5e-bac8-0798ef06c1ff.jpg)
/picture_3ad0be25-f71e-4625-a9f3-0d496c2a0738.webp)
/picture_2cf0799f-11fa-4c9b-aa6c-6205d84ff532.jpg)
/picture_9a904d39-cf13-433f-b52f-bb9607cd847e.webp)
/picture_a5012754-5ed5-4620-b152-d5449bf7383c.webp)
/picture_fc58fd1f-fc81-4eff-ba85-10aef10b30f5.jpeg)
/picture_8b76d9c3-48c0-4575-a993-c5e5b92bf3b4.jpg)
/picture_daddddb7-bdd5-46d6-9401-170b1464920a.jpg)
/picture_43bca09f-e3a1-4fa2-ac21-516cf1995c69.jpg)
/picture_288328d1-7104-426e-b2c6-7ff4f03f3be4.webp)
/picture_d66a7393-ae61-4f00-8b7e-8433d73999a6.png)
/picture_c56edf2c-3f61-478b-8e85-24fc268e2c84.jpg)
/die-siedler-von-catan_thumb_1.bing_en.jpg)
/dominion_thumb_37.bing_en.jpg)
/picture_d2713af1-45bb-4f3f-bfcb-3a40d059c061.jpg)
/picture_54e881df-ed6a-4865-8f08-290676842639.jpg)
/picture_223cfea0-36a5-4041-912f-1bf086330158.jpg)
/picture_3a2dc9ac-11d9-4ace-9556-6eb1bf6f180b.jpg)
/picture_aa1601fa-59ef-497c-8510-6ae7e1d530fc.jpg)
/picture_f1858e77-7867-4d37-9b90-67cb9548d22e.jpg)
/picture_868b38ad-f427-40a0-b4d1-645c78fc204b.jpg)
/picture_836d5f4d-8cbd-4c6c-b59f-45d43654e0da.jpg)
/picture_cf725a25-82dd-4dae-bd2f-68755461b0a5.jpg)
/agricola-2.jpg)
/7-wonders3.jpg)
/picture_585611a3-ca1e-484b-b32e-1d4bb4685a6d.jpg)
/picture_bd9a68ee-5ced-420e-b599-efa735e30bcc.jpeg)
