- 1人~2人
- 60分前後
- 12歳~
- 1976年~
ヨーロッパ上空の戦い / エアフォースBluebearさんのレビュー
第2次世界大戦における航空機の戦闘を再現したシミュレーションウォーゲームの傑作。
もともとはBattle Line社から発売されていたものを大手のAvalon Hill社が買い取って1976年にリリースされました。(その後ホビージャパン社から日本語版の発売もされました。)
航空機1機単位での3次元における空中戦を、ここまでシンプルなデザインで完成させた作品は他にほとんど例がなく、アナログ処理ゆえの欠点はいくつもあるものの、歴史的な金字塔であることは間違いないでしょう。
この作品は、1ターン10秒、ボード上の1ヘクスは500フィート(約152メートル)のスケールで、航空機1機単位の空中戦機動を再現し、相手の機の撃墜を目標とします。
もう40年以上前に、ホビージャパンから詳細な日本語解説書付きで発売され、大人の知的な遊戯としてちょっとしたブームになったシミュレーション・ウォーゲームの初期紹介作品のひとつです。
『Submarine』でUボートと駆逐艦の熱い対決に感動し、『PanzerBlitz』でタイガー戦車の進撃に心震わせた私が次に手を出したのが《空戦》だったのは必然でした。
/post_image_d58ee68e-9688-4741-b3bd-31b3d81580c4.jpeg)
↑古いゲームなので、もうボロボロですね(感慨)。
/post_image_40bb4444-0c94-4f56-8cd9-cee7d55387a0.jpeg)
■内容
厚紙打ち抜きの航空機コマ。(色分けした荒っぽいシルエットと識別番号だけ、というちょっと味気ないデザイン。同機種バリエーションも同じ駒を使う前提なので、コスト的に仕方なかったのですね。)
大空を表すのになぜかクリーム色っぽいマップボード6枚。(継ぎ合わせて大空の広がりを表します。…でも紙質が悪くなぜかものすごく反り返って曲がる…)
/post_image_72937cab-965e-4e01-92b2-3e87a29f7900.jpeg)
航空機の機動を記録する専用の記録用紙の束。
/post_image_b2f752df-a35e-488e-9da9-d51b46843648.jpeg)
そして極め付きは…
両面フルカラーの航空機データカードが15枚(合計30機分のデータ)です!
(この基本セットではおもに西部戦線における航空機のデータでしたが、こののち太平洋戦争のアメリカ機、日本機のデータセット『DAUNTLESS』、さらにヨーロッパ東部戦線他各種の追加機種セット『EXPANSION KIT』が発売されました。)
このデーターカードが非常によくできており、航空機のメーターをイメージした半円形の図式の中に、色分けされて各航空機の性能の違いが詳細に描かれていたのです。
慣れないとなんだかさっぱり分からないくらいの情報量ですが、一度見かたを理解すると実にわかりやすく整理されていることがわかります。
(当時これを見比べているだけで数時間没頭できたものです)
/post_image_30dd7822-9169-46db-b273-58c956b417a5.jpeg)
/post_image_ac02e643-d30b-4ce6-90ff-70b9e058ab6b.jpeg)
↑使い込んだものなので、書き込みとかいろいろあってすみません。(自分が分かればいいのであまり抵抗ないんですよ。)
/post_image_b8a283e7-6932-430a-92cf-7f588ad57a9e.jpeg)
↑データの見方はルールブックにあります。
■主なルールと特徴だけ紹介
①高度によって性能は変わる
戦車戦などと違って航空機は空中を立体的に機動します。この立体(3次元)というところも厄介なのですが、空は《高度》によって空気密度が違うので、エンジン性能も変われば、空気抵抗も変わります。
そのためこのゲームでは高度をフィート単位でいくつかに分け、発揮できる性能が違うことをシンプルに表現しました。
もちろん1ターンに上昇・下降できる高度の違いも、データーカードに細かく指定されています。
もっともボードだけは平面なので、お互いに「今高度は〇〇フィート」と申告し合わなければなりません。空中の立体感だけは残念ながらどうしようもありませんね。
②飛行機は急に加速減速できない
地に足が付いていない航空機はエンジンパワーを上げてプロペラをもっと回しても、すぐにはスピードが上がりません。また当然急には止まれないので、エンジンパワーを下げたり、エアブレーキを使って少しずつ減速するしかありません。
この《いくつ加速できるか》《いくつ減速できるか》は、航空機と高度によって決められており、前のターンに決めた量だけ、次のターンのスピードが変化するのです。
つまり自機のスピードのコントロールは、状況を良く判断して計画していかないと、自分の思った通りの移動ができないのです。
さらに各機体ごとに、速度区分を色分けして分かりやすくしてあります。
失速速度(これを切ると墜落します)→■青
運動速度(空中戦に最も適した戦闘速度)→■緑
水平速度(機体に無理なく高速でまっすぐ飛ぶ速度。運動性は少し落ちる。)→■黄色
降下速度(降下することで通常より高速で飛行する速度。これを越えると機体が分解!)→■赤
このように、速度によって運動性がかわるところまでちゃんと細かく再現されているのです。
(この色分けによって、その航空機がどのくらいの速度&高度の範囲で最大限の性能が発揮できるかが一目でわかるのは凄いと思いませんか!?)
③飛行機は急に曲がれない
飛行機の移動で最大の特徴がこれです。
飛行機は翼面積や機体重量、推進力、遠心力などが影響し、曲がりたいところですぐに曲がったりしません。
例えば右に曲がりたいときは機体を右にバンク(機体を右に傾けること)させ、機体を引き起こす要領で大きく旋回します。このときどのくらいの半径で旋回できるかは、機体の高度や速度など様々な条件で決まってきます。
このゲームではそれをシンプルなデータカードで一覧にまとめ、手軽に再現できるようになっているのです。(3ヘクス進んで右バンク、さらに4ヘクス進んで右旋回、また3ヘクス進んで機体を水平に戻し…という感じです。)
敵が右にいるから「今すぐに右に曲がりたい!」と言っても、そう簡単にはいかず、ある程度決められた距離を進まないと曲がることができません。
これによって航空機ごとの旋回性能が違ってくるのです。
航空機同士の空中戦(ドッグファイトと言います。互いに相手のしっぽに嚙みつこうとしてぐるぐる回る犬に例えています)では、どのような旋回運動で機体を飛ばすかによって、どう動いたら相手の後ろに付くことができるかどうかが勝負を分けますから。この機体運動はものすごい大事です。
④高速での戦闘は一瞬の判断で決まる
戦闘機の空中戦は1瞬の判断が生死を分けます。
実際にこのゲームの時間スケールは、1ターンが実際の10秒なので、あれこれ考えている余裕はありません。じゃあこの《短時間》をどうやって再現したかというと、それが《記録用紙》なんです。
各プレイヤーは、次のターン(次の10秒)にやりたいことを計画し、すべて記録用紙に記入します。(どのくらいスピードを変えるのか、上昇するのか下降するのか、機体をどっちへ旋回させるのか、といった内容です)
全員が記入し終えたら一斉に公開して、計画通りに機体を運動させることになります。
相手の動きをちゃんと見てから自分の動きを考える、といったプレイではないのですね。ここがまさに機動戦の醍醐味です。
⑤激しい読み合いの連続
これらの独特なルールによって、ゲーム中はかなり激しい読み合い(心理戦)となります。
ここがたまらなく楽しい!
正面から突っ込んでくる敵機をどちらからかわすか悩んだり、左に急旋回すると思ったのに、急反転して右旋回を始めたり、いかに自分の攻撃の間合いに敵機を捉えるか、またいかに敵機の攻撃の間合いから逃れるか、必死で腹の探り合いをするのです。ここがボードゲームとして優れているところです。
「アイツのことだから絶対加速して逆方向へ反転するにちがいない!」とかを常に考えるわけです。
しかし、せっかく相手の真後ろに喰いつこうと思ったのに、相手に急減速されて追い越してしまい大爆笑なんて事態も起こります。
ほら、ちゃんとボードゲームとして成立しているでしょう?
⑥慣れれば編隊飛行も可能
ゲーム手順に慣れてくると、《例外処理》がかなり少ないことが分かります。(宙返りなどの特殊機動を除く)
これはアナログゲームのルールを考える上で、かなり優秀なポイントのひとつなのです。(それだけ基本設計が優れているということです。練習用の1人プレイシナリオのできも大変よろしい♪)
そのため、ある程度慣れてくると無理なく一人で4機編隊くらいまでを同時に扱うことが可能です。
自分が1機単位で戦っていると選択肢が限られてくるのですが、複数機体で戦うと、別の機体が回り込んだり、囮になったり、援護したり、チームワークを駆使した様々な戦略が取れるようになり、さらに戦略性がアップします。
(これは個人視点のみのフライトシミュレーターでは不可能な特徴ですね)
また、人数が集まれば2vs2、3vs3の勝負も盛り上がりますよ。
第二次大戦時の零戦やメッサーシュミットBf109などの航空機が好きな人には、ぜひどこかでプレイしていただきたいゲームです。(日本軍機は拡張版の『DAUNTLESS』がないと手に入りませんが。アメリカ人デザインなので、日本軍機の性能評価がだいぶ辛口になっているのが複雑なところです…)
有名どころの機体はかなり網羅してあるので、歴史的な設定など無視して、自分の好きな機体を選びあって、自由に対戦を楽しむのが一番のプレイスタイルだと思います。
ルール説明には30分もかかりませんし、1ゲームは長くても1時間程度(短いときには15分くらいで決着が付くことも。)
1回やると、絶対に次は違う機体で出撃したくなりますよ!
【余談①】
現代はデジタルゲームが進化していて、リアルなグラフィックの優秀なフライトシミュレーターが多数出ています。
こんな時代に実際の時間10秒単位のゲームを、何分もあれこれ考えながらボードゲームでやるなんてリアルじゃない!という批判があります。
確かにアナログゲームの自分手番を実際に10秒でやる、というのはあまりに非現実的です。でも実はその《リアル》を求めているわけではありません。
実際の空中戦でドッグファイトに至る戦闘機パイロットは、訓練を受けたプロですが、我々プレイヤーはしょせん素人なのです。プロの戦闘機パイロットが10秒の間に判断してやることを、素人のプレイヤーが何分も考えて手順処理するくらいのほうが逆にリアルなんじゃないか、と考えています。
【余談②】
前述のように、このゲームはリリースが古いこともあって、ボードやコマの作りがちょっと雑です。
そのため私は途中から、ツクダホビーの『撃墜王』の美しい空ボードと、完成度の高い航空機コマを流用していました。この当時のツクダホビーのコンポーネントのレベルはずば抜けて高く、非常に応用範囲が広かったです。(ゲーム自体は複雑すぎて1回しかプレイしませんでした。笑)
/post_image_a02488e6-400e-4a89-85da-f43f2a435cbc.jpeg)
↑これ、とりあえずボードだけツクダ製。全然雰囲気が違うなぁ…。
【余談③】
BGGを検索してみると、改訂されたデータカードがもの凄い大量に公開されています。
興味がある人はダウンロードしてみるといいですよ♪
- 12興味あり
- 36経験あり
- 12お気に入り
- 29持ってる
Bluebearさんの投稿
/post_image_cd6938ef-3b0d-467d-9e6d-4d1b0ba9ce1b.jpeg) レビュートーネードスプラッシュ水しぶきをあげて疾走する水上バイクの熱いレースを、アナログ手法で見事に...3ヶ月前の投稿
レビュートーネードスプラッシュ水しぶきをあげて疾走する水上バイクの熱いレースを、アナログ手法で見事に...3ヶ月前の投稿/post_image_cec6fd5e-db80-4509-894f-3b79a022f136.jpeg) レビューこの世の武器は僕のものファンタジー世界を舞台に、6種類の伝説の武器を集め、よりたくさんのお金...3ヶ月前の投稿
レビューこの世の武器は僕のものファンタジー世界を舞台に、6種類の伝説の武器を集め、よりたくさんのお金...3ヶ月前の投稿/post_image_523060dd-6930-495f-9edf-92d84c4a83b3.jpeg) レビューこっちよネコちゃん / 猫との距離猫が大好きな人向けにデザインされた台湾製のコンパクトなゲーム。2024...3ヶ月前の投稿
レビューこっちよネコちゃん / 猫との距離猫が大好きな人向けにデザインされた台湾製のコンパクトなゲーム。2024...3ヶ月前の投稿/post_image_470da329-2bfe-4f00-80a2-9544a2a50d84.jpeg) レビュースピリッツ・オブ・ザ・フォレスト大いなる存在のひとりとなって、森を再生させるためにそこに棲む精霊たちの...4ヶ月前の投稿
レビュースピリッツ・オブ・ザ・フォレスト大いなる存在のひとりとなって、森を再生させるためにそこに棲む精霊たちの...4ヶ月前の投稿/post_image_9d1026bb-eca7-4ca6-a3a1-43f4a03a3327.jpeg) レビュー第二次欧州大戦フルマップ9枚という、少なくとも8畳間全域に広げないと人の座るスペース...4ヶ月前の投稿
レビュー第二次欧州大戦フルマップ9枚という、少なくとも8畳間全域に広げないと人の座るスペース...4ヶ月前の投稿/post_image_17c258d9-5048-4238-9f31-b6487019fbc5.jpeg) レビューグロウ ~トモシビノタビ~2021年に、『ルイスクラーク探検隊』『ディスカバリーズ:ルイス・クラ...5ヶ月前の投稿
レビューグロウ ~トモシビノタビ~2021年に、『ルイスクラーク探検隊』『ディスカバリーズ:ルイス・クラ...5ヶ月前の投稿/picture_9ee11ab9-4fb8-43d5-b697-6a40e0e289b4.jpg) レビューダンジョンダイスオンライン2022年に同人作品でリリースされたものが好評で、2024年にクラウド...7ヶ月前の投稿
レビューダンジョンダイスオンライン2022年に同人作品でリリースされたものが好評で、2024年にクラウド...7ヶ月前の投稿/picture_74cd889e-a670-4daf-8d19-72f32ada842a.jpg) レビュークイナガン同人制作の2丁銃バトルゲームの『ガンナガン』の設定と、カナイセイジ氏の...7ヶ月前の投稿
レビュークイナガン同人制作の2丁銃バトルゲームの『ガンナガン』の設定と、カナイセイジ氏の...7ヶ月前の投稿/post_image_233f34f8-acf3-4b09-b5b8-4dbdf8480061.jpeg) レビュー花嫁が多すぎる少年マガジン連載だった春場ねぎ氏の漫画『五等分の花嫁』をテーマにしたカ...7ヶ月前の投稿
レビュー花嫁が多すぎる少年マガジン連載だった春場ねぎ氏の漫画『五等分の花嫁』をテーマにしたカ...7ヶ月前の投稿/picture_45d66b7b-3f5f-4015-84da-cc6f4b3fc357.jpg) レビューウィキッド・フォレスト大切な人を助けるため、邪悪な魔女の住む森の奥深くへ行き、『穢れの花』を...7ヶ月前の投稿
レビューウィキッド・フォレスト大切な人を助けるため、邪悪な魔女の住む森の奥深くへ行き、『穢れの花』を...7ヶ月前の投稿/picture_6b13348e-d8c5-4ce3-bcc8-6119a25bfc5a.jpeg) レビューアローン:ディープ・エクスパンションあのSFホラーボードゲーム『アローン』の第2拡張セットです。元のゲーム...9ヶ月前の投稿
レビューアローン:ディープ・エクスパンションあのSFホラーボードゲーム『アローン』の第2拡張セットです。元のゲーム...9ヶ月前の投稿/picture_cb1f22de-3625-4689-b3ec-c5ac69da9611.png) レビューアローン2019年にイタリアのHorrible Guild社からリリースされた...9ヶ月前の投稿
レビューアローン2019年にイタリアのHorrible Guild社からリリースされた...9ヶ月前の投稿
会員の新しい投稿
/picture_0f76b34d-45e1-47f6-b88b-aec9f975f19f.jpg) レビュール・アーブル3人プレイ。インスト30分プレイ2時間半程。18ラウンドもあるので超時...24分前by oliber
レビュール・アーブル3人プレイ。インスト30分プレイ2時間半程。18ラウンドもあるので超時...24分前by oliber/post_image_255f8cec-dbbb-400c-af46-ecc081eb03f6.jpeg) レビューフォレストリー林業の集大成ボードゲーム。森林の管理人となり、伐採機を運転したり、製材...約4時間前by 荏原町将棋センター
レビューフォレストリー林業の集大成ボードゲーム。森林の管理人となり、伐採機を運転したり、製材...約4時間前by 荏原町将棋センター- リプレイけろりんむらの田植えソロプレイルール【タイムアタックパズル】で遊んでみました♪\(^ワ^)...約4時間前by あんちっく
/picture_40ece8bc-f354-46ee-99ff-04315429638b.jpg) レビューモンスターヘクス500種類以上のボードゲームを遊んできた経験をもとにレビューしています...約7時間前by てう
レビューモンスターヘクス500種類以上のボードゲームを遊んできた経験をもとにレビューしています...約7時間前by てう/picture_35a299ab-dab4-4e16-bd66-d447d8393486.jpg) レビューペンギンパーティインストがメチャメチャ簡単なので、とりあえず遊ぼう!逆ピラミッドソリテ...約8時間前by oMaMe
レビューペンギンパーティインストがメチャメチャ簡単なので、とりあえず遊ぼう!逆ピラミッドソリテ...約8時間前by oMaMe/post_image_36bdea40-53d5-4289-8aad-0629917059dd.jpeg) レビューヘックメック鳥になって虫を集めるサイコロゲーム。友人2人と小5の男の子の4人でプレ...約9時間前by レモネード
レビューヘックメック鳥になって虫を集めるサイコロゲーム。友人2人と小5の男の子の4人でプレ...約9時間前by レモネード/post_image_3658d72e-88f3-4f21-b748-b122a123ae34.png) レビューカントリーサイド田舎暮らしはゆったりするだけなく、作物を育てたりとなかなかに忙しい。育...約10時間前by うらまこ
レビューカントリーサイド田舎暮らしはゆったりするだけなく、作物を育てたりとなかなかに忙しい。育...約10時間前by うらまこ/picture_84d08f9e-58d6-412d-a4fa-54f26d4e7707.jpeg) レビュークォーリアーズ!:験闘士の探求(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ
レビュークォーリアーズ!:験闘士の探求(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ/post_image_ffd16765-6555-440d-9c18-eaf7e864a9c5.jpg) レビュークォーリアーズ!:最終決戦(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ
レビュークォーリアーズ!:最終決戦(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ/picture_6813831b-3cb7-4ba2-b07b-e95012e003a4.jpeg) レビュークォーリアーズ!:魔神到来!(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ
レビュークォーリアーズ!:魔神到来!(拡張セット)☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約11時間前by くつろぎ/picture_20081c07-649f-48b2-913a-cb8c4329d645.jpeg) レビュークォーリアーズ!☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約12時間前by くつろぎ
レビュークォーリアーズ!☆推奨最低人数:2人☆インスト難易度:5/10☆リプレイ性:8/10☆...約12時間前by くつろぎ/picture_09630af1-82c3-4c2f-9387-4241ed8d1450.webp) レビューグレート・ウエスタン・トレイル:第2版6/10(BGAでプレイ)グレートウエスタントレイル(以後、GWT)が...約13時間前by 白州
レビューグレート・ウエスタン・トレイル:第2版6/10(BGAでプレイ)グレートウエスタントレイル(以後、GWT)が...約13時間前by 白州

/post_image_8d0c5541-62f5-4ac5-b78c-9862ba325d9c.JPG)
/advertise/banner-20260109.png)

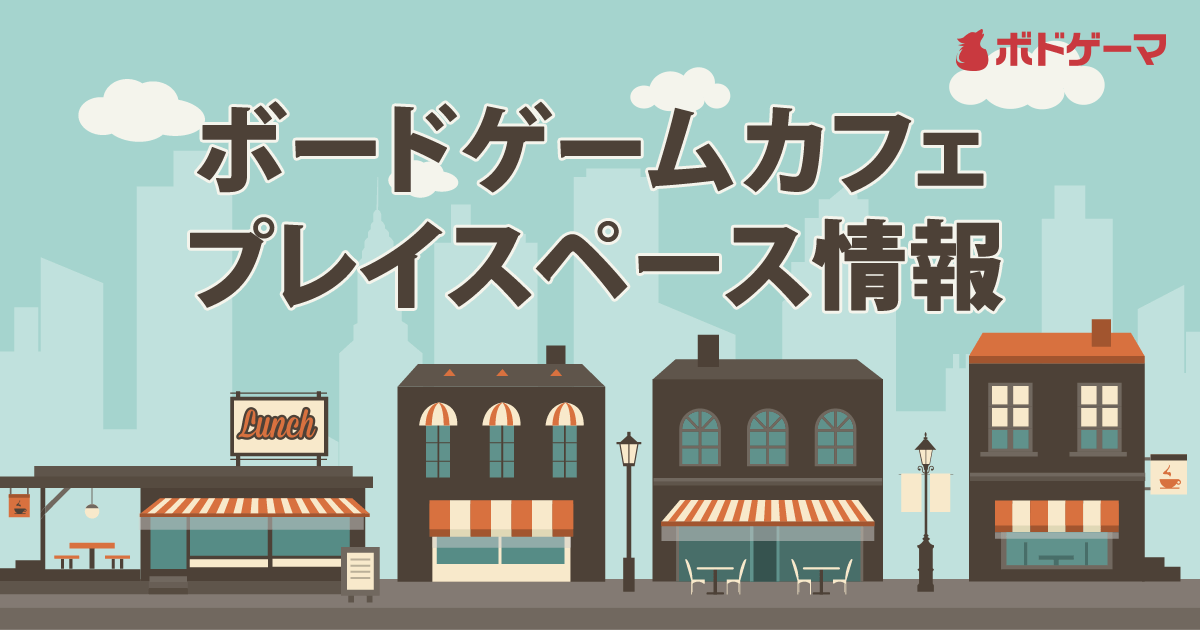
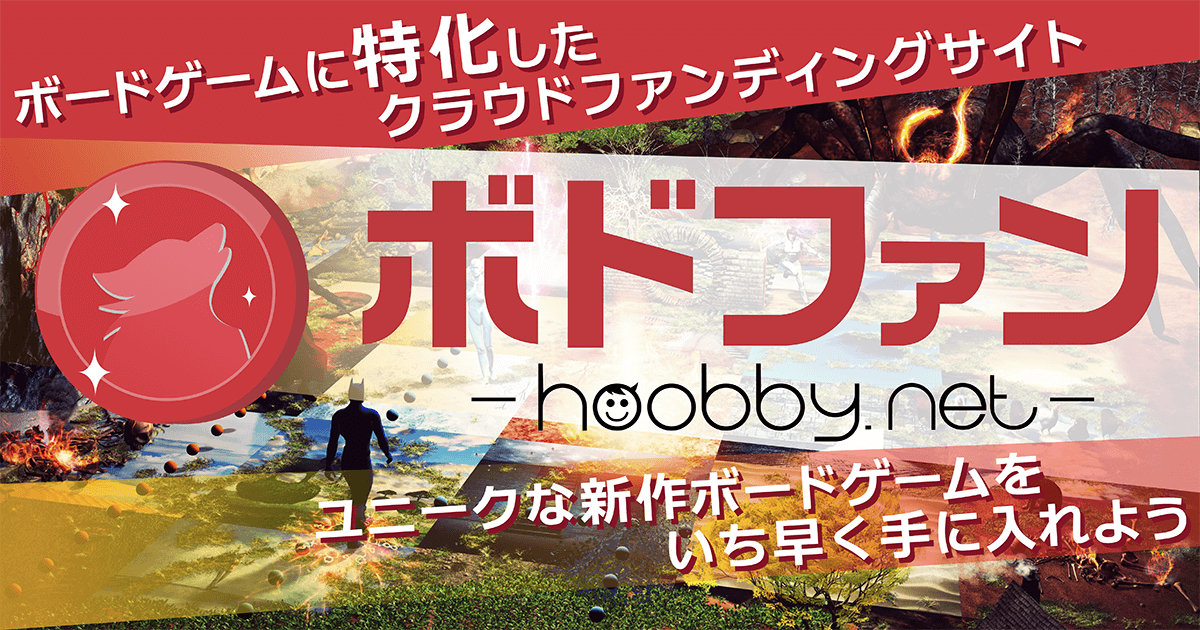
/picture_369113fc-8bda-4228-a914-e16622e83054.jpg)
/picture_06d9da5e-2ba2-4c9c-adcd-5f8bad516665.jpg)
/picture_76b4a374-7096-49d7-bade-d9a6a710e794.jpg)
/picture_7067ceff-e29d-425a-b499-e209d9985918.jpeg)
/noimage_game.png)
/picture_6c1ea311-6f8f-4d96-acbf-9b3807c60bb2.webp)
/picture_d9910a5d-cfc4-40f9-bf15-f9f32bdc362b.jpg)
/picture_79d56e8d-f209-4a28-a64a-8493139e22cc.jpg)
/picture_7f470740-5f02-4142-9786-954c33d0e3e5.png)
/picture_e1d9b608-f46e-4fed-bd9f-46560a4b4851.png)
/picture_9dd5e67a-9c64-4e57-bea8-dd02ba7f2bff.webp)
/picture_e8b68f74-c654-435c-adb4-45554e0ab8a0.jpg)
/picture_bd7905f7-93e7-4be2-a8f9-dbe2eace06a8.png)
/picture_60fc6aa8-3ed6-40c8-9fa8-471b3850c193.jpg)
/picture_d9f7d519-fab1-4706-b54f-37f087fce9ca.jpeg)
/picture_5f8a6bbb-2dca-4f1d-acee-beaf0bd58ff4.webp)
/picture_e59b0ad8-05a8-4438-891f-e975fb845342.webp)
/picture_1db6c204-7d10-44a4-8b28-750832c9ce36.jpg)
/picture_b693c763-54f3-46dc-9c90-e08399c30baf.jpg)
/picture_b34c05ef-cf0c-4efb-9bb1-49fb5e5f5ed2.webp)
/picture_c56edf2c-3f61-478b-8e85-24fc268e2c84.jpg)
/die-siedler-von-catan_thumb_1.bing_en.jpg)
/dominion_thumb_37.bing_en.jpg)
/picture_d2713af1-45bb-4f3f-bfcb-3a40d059c061.jpg)
/picture_54e881df-ed6a-4865-8f08-290676842639.jpg)
/picture_223cfea0-36a5-4041-912f-1bf086330158.jpg)
/picture_3a2dc9ac-11d9-4ace-9556-6eb1bf6f180b.jpg)
/picture_aa1601fa-59ef-497c-8510-6ae7e1d530fc.jpg)
/picture_f1858e77-7867-4d37-9b90-67cb9548d22e.jpg)
/picture_868b38ad-f427-40a0-b4d1-645c78fc204b.jpg)
/picture_836d5f4d-8cbd-4c6c-b59f-45d43654e0da.jpg)
/picture_cf725a25-82dd-4dae-bd2f-68755461b0a5.jpg)
/agricola-2.jpg)
/7-wonders3.jpg)
/picture_09c7c42c-8008-475c-9188-e8a7f3d67d51.jpg)
/picture_7e4bba22-490a-4821-82d6-3d57fc8d4cb0.jpg)
